オフ会で会ったレナちゃんからの LINE を菊池さんに見られてしまった友崎くん。
???「人生において『キャラクター』になって、楽しく生きる」
自分の行動が、意図せず人を傷つけてしまったとき。
その傷つけてしまった相手が、自分にとって大切な人であったとき。
相手にも自分にも誠実でいるためには、人はそれをどう贖うべきなのだろうか。
こんなヤバイやつらが集まったクラスはオレっちなら嫌です^ー^
まぁ、変人奇人にしないと物語に深みがでませんからね^ー^
俺っちと一緒に弱キャラを読み始めたキモオタはリタイアしました。
「キモすぎて無理」らしいです^ー^
俺っちはキモオタのキモチを理解したいので読みますが^ー^
オフ会などで菊池さんとの2人の時間を作れなかった友崎くん。
中村と泉に声をかけられます。
菊池さんは、泉と LINE をする仲になったそうです。
友崎くんはアタファミのオフ会に行っていることなど近況を話します。
その折、菊池さんと出くわします。
菊池さんが開口一番に言ったのは……
「ごめんなさいっ!」
「その……友崎くんがどんなLINEをしてたかとかってより……それを勝手に見たのって、よくないと思うから……」
そんなふうにしばらく押し問答が続く。しかも互いが互いに、自分のほうこそ悪いのだと主張しているというあべこべな状況だ。
そこで俺は思い出す。
中村と泉も言っていた。
解決するには、二人でしっかりと話すしかないのだと。
こうしてできた二人の関係。
俺はまだ菊池さんのことを理解しきっているわけじゃないけれど、それでも他の人よりは深く関わってきたつもりだ。
だからきっとわかる。この二人の関係性なら、言うべきことは。
俺は微笑みをつくりながらも、はっきりと言う。
もしもなにか間違ったことをしてしまったのだとしても、それをきちんと話して謝って互いに納得すれば、それは許されるべきだから。
もしかするとそれは、俺の過ちを許して欲しいという願いの表れであるのかもしれないけれど。
きっと菊池さんと話すときはこうしてしっかりと言葉を使って、一つ一つ積み重ねていくように、なるべく理想的と思える方向へ向かっていくのがいいはずだ。
そしてそれが俺の肌にも合うからこそ、二人はつながれたのだとも思う。
そして、菊池さんは友崎くんのことを応援しているといいます。
『3.3.7ビョーシ!!』って作品をみんなは知っているかな^ー^?
「私は……友崎くんのことを、応援してるんです」
「応援?」
「オフ会に行ったり、花火ちゃんのお店に遊びに行ったりしたことも、……ちょっとだけ、寂しくはあったけど。
友崎くんが将来のこととか、自分の目標を考えるためにしてるんだってことはわかってて。
……そうじゃなくても、友崎くんが世界を前向きに広げていくのは、私にとっても嬉しいことなんです」
「……ありがとう」
思いのままに伝えられる言葉は、それでも俺のことを尊重してくれていて。
「だから私は、それを邪魔したくはない、応援していきたいって、思ってるんです。……そ、その……彼女、として」
「友崎くんにとっての世界はきっと、私が生きてる炎人の湖よりも広くて。だからきっと、私じゃない人と過ごす時間だって、友崎くんにとっては大事なもので」
「……炎人」
その言葉だけを、小さく繰り返した。
演劇で一緒に脚本を作ったとき。ポポルについて、そして菊池さんの価値観について話したときに、キーとなった存在。
──決まった環境でしか生きられない、閉ざされた種族だ。
「だから……私のわがままだけで、友崎くんの世界を壊したくはなかったんです」
「友崎くんは炎人じゃなくて……ポポルだから。友崎くんが自分の道のために世界を広げていくことは、素敵なことだから」
「私と友崎くんはその……えっと、付き合ってる、けど……それでもまったく同じ人生を生きてる二人ではないんだってことは、わかってたつもりで。だから私はそれを尊重しなくちゃいけないってことも、わかってたんです」
この作品のテーマは「尊重」です。
日南との関係もそうですけど、菊池さんとも同じことです。
「ちょっとだけ──寂しくなっちゃったんです」
言いながら、どこか自嘲的に笑う。
俺は菊池さんのその表情が切なくて。穴があくような重みが、下腹部にずしりと沈み込んだ。
「ごめん、だったら俺、菊池さんにも声をかければよかった」
しかし菊池さんは、ゆっくりと微笑えんで首を横に振る。
「ううん。それもきっと、違うと思うんです」「違う?」
聞き返す俺に、菊池さんは頷うなずく。
「だって、友崎くんが教えてくれたから」そして、俺に優しく微笑みかけた。
「無理しないで、棲すみ分けてもいいんだって。──炎人のいる湖で、仲間を探せばいいんだって」その言葉に、俺ははっとする。
「……そっか」
それは、俺の言葉。
自分は変わらなければいけないのかと迷っていた菊池さんに、俺が提案した一つの答え。
学校というコミュニティが自分に合わないのなら、無理にそこで生きる必要はない。それは人が生きるべき、唯一の道ではない。
「……たしかに俺は、いまでもそう思ってる。自分を変えることだけが、正解じゃない」
「湖のなかから、世界を広げていく友崎くんを見ているのは、私にとって自然なことのはずで……」
震えるように動く唇くちびるから漏れる声は、やっぱりどこか寂さびしげで。
「私は炎人で、友崎くんはポポルだってわかっていて……私はこの関係を受け入れたはずなんです」
「──けどそれとは別に、遠くで楽しんでいる友崎くんを見て、嫉妬してしまってる自分もいたんです」
「たしかに友崎くんは炎人である私を選んでくれたけど……私が湖の外に出られるわけではなくて」
もしも、矛盾した関係に言葉で理由をつけて結び合わせたその接ぎ目から、なにかが漏れはじめているのだとしたら。
「自分が湖から出られないというだけなら、その世界を受け入れればいいんです。自分が生きられる世界で、自分の感情に合う言葉を探せば解決します」もしも、自分のなかだけでなく、誰かとのつながりや関係性のなかに矛盾があるのだとしたら。
そのときはなにを変えて、なにを貫けばいいのだろう。
「湖から出られない炎人と結ばれたのが、あらゆる種族と仲良くなれるポポルだったのだとしたら。──炎人は、ポポルは、どうしたらいいんでしょう?」
ドラマやマンガといったメディアにあるような方法で距離を詰めようとする友崎くん。
そして俺は、菊池さんの家の最寄りである北朝霞か駅まで来ている。
「えっと……わざわざありがとうございます」
俺がファミレスで恥ずかしいことを言ってしまったあと。しばらく二人で話し合った俺たちは一緒に溝を埋めるための方法を探し、ここのところすれ違ってしまっていたぶん、なるべく一緒にいる時間を増やそうと決めた。
ならばということで俺は、外も暗くなってしまっているし、自分のなかの恋愛のイメージによくある『送って帰る』というものを実践しようと提案したのだ。ていうかこういうことすら全然やってなかったのがダメだったのかもしれない。
「友崎くんは……どうして私を選んでくれたんですか?」
秘め事を漏もらすようにぽつん、と落とされた質問。俺はそれを優しく拾い上げるように、大切に声のトーンを作った。
「どうして……って?」
「その……友崎くんの周りには、魅力的な女の子がたくさんいるのに、なんで私だったのかなって」
「えーと、それは……」
俺は少し考え、やがて一つの答えに行き着く。
だってそれは、あのとき図書室で話したことだ。
「仮面と本音とか……理想と気持ちとか。そういう矛盾のなかでまったく逆の方向に悩んでて、けどそれは考えてみると同じことで……。それが奇跡みたいで、特別だって思えたから……かな」
「物語から菊池さんのことが見えてきて……それが俺にとって、魅力的だったり、その……守りたい、みたいな、そういう感情にもなって」
俺は二人で過ごした大切な時間を思い出しながら。
「そのなかで、菊池さんの真剣な姿とか、自分の難しい問題を乗り越えたときの前向きさみたいなものが、すごく輝いて見えたというか……」「う、うん……」
それは本音だから、言えば言うほど俺は照れていき、それが本音であることがたぶん伝わっているから、菊池さんも顔をどんどんと赤くしていく。
「もともと考え方が似てたってところもあったけど……だからこそ菊池さんの悩みが理解できて、それを乗り越えていくことに、共感というか、ドキドキみたいなものがあって……」「わ、私は……。いつ見ても前に向かって進んでて、自分の世界を広げていく友崎くんのことをずっと、尊敬してて……」
「だから私は、友崎くんが世界を広げていくことを……ポポルでいることを、やめてほしくないんです」
翌日、菊池さんと一緒に登校する友崎くん。
文化祭の演劇の脚本と監督で付き合い始めたカップルという噂は広まっているようです。
どうやら、3年生を送る会で記念品「運命の旧校章」を贈呈する文化があるようです。
旧校舎で使われていた校章を3年生が2年生に渡すようですね。
「それを受け取った二人は、卒業まで校章が幸せを運んでくれて……卒業したあとも、ほかにはない特別な関係になれる、って言われてるの!」
「とても、ロマンチックな伝統ですよね」
「あはは。たしかに、なにかの物語みたいだね」
「それを受け取る役割、友崎と風香かちゃんにやってほしいなって!」
「わ、わたしたちに……!?」
「ほら、二人って、文化祭であの演劇作った公認カップルだし、こういう役割にぴったりだと思うんだよね! 学校の人にも結構知られてるから、すごい特別感あるじゃん!?」
休み時間に水沢が近づいてきます。
一緒に登校すると行った行動をとるからこそ不仲ではないかというのです。
「形式」に拘るというのです。
ドラマやマンガ、アニメ、ゲームがつくりだした恋愛の形式にとらわれているというのですね。
旧校舎の校章を渡すのも形式なんですけど^ー^
そして、人生攻略、友人関係、恋愛、アタファミ……いろんな事柄を上手く進めていく友崎くん。
全てのことに全力投球はできないと水沢は言います。
恋もジョストも勉強もなんてうまくはいきませんからね。
優先順位って知ってる^ー^?
「気持ちよりも行動とか、そういう……?」
「んー近いけどちょっと違うな。っていうか、文也も直感ではわかってるはずだぞ?」
「え?」
思わぬ言葉に、俺は困惑する。
「だってお前、仲直りのために『家の前まで送る』とか『朝は二人で登校する』とか、そーいうカップルっぽいことをしていこうって決めたわけだろ?」
「……あ」
俺が気がついて声をあげると、水沢はやたら偉そうにドヤ顔をした。
「わかったか?」
「つまり俺はいま、恋愛としての〝形式〟をやってってるってことになる……?」
「けど、それってさ。──正しいけど、文也っぽくはないんだよな」
「……どういう意味だ?」
「んー。なんつーのかな」
「形式ってのはあくまで表面を取り繕うためのもので、本質じゃないだろ」
「だから俺は、チャラ男的にとりあえず形式だけ整えてあげればいいとは、思わなくなってきたんだよ。……少しずつ、だけどな」
「なのに文也やがやってることは、ある意味その場しのぎっていうかさ。だって、いくらあとで飴をあげても、文也がオフ会に行ったり、友達とも遊んだりする男で、菊池さんがそうじゃない女の子だってことは変わらないんだから」
「……そうだな」
俺は頷うなずき、昨日のことを思い出す。
二人の関係はポポルと炎人なのだと、菊池さんは言った。
「そういうところ潔癖なはずの文也が、そうしてるのはちょっと不思議だなーって。文也なら、『じゃあそもそもオフ会に行かない』とか、言い出しそうだろ」
「あ。別に、それが正しい解決とは思わないけどな? けど、文也はそうしそーだなって」
「だな……」
言われてみれば俺も、今回自分がした解決法は俺らしくないというか、どこか『恋愛』というもののイメージに頼ったもので、根本的な解決ではない気もしていた。
にもかかわらず俺は、根っこからひっくり返すような方法は選ばずに、形式を選んだのだ。
どうして俺は、今回に限ってそっちを選んだのか。
しばらく自分に問いかけると少しずつ、言葉が出てくるのがわかった。
「たぶん……俺にとってオフ会は自分の将来に関わることだし、仲良くしてるみんなとの時間ももちろん、ずっと楽しかった時間だし……これから仲良くなれそうな人との遊びだって、自分が人生を広げていくために、やりたいことなんだよ」
「文也はさ。恋愛を適当に誤魔化かそうとしてるんじゃなくて──」
「将来のことも、友達のことも、恋愛のことも……全部同じ重さで考えてるんだよ」「たしかに俺は……対戦会も、もともと仲がいい友達との時間も、これから広げていく人生のことも……菊池さんとの時間と同じくらい、優先したいって、思ってる」
「文也の時間は限られてるから、全部を選ぶってわけにはいかないだろうな」
「本当に真剣に向き合うなら、選びたいものだけを選ばないといけないんだよ。で、お前はそれを放棄してると」
「で、いまは手のひらから菊池さんがこぼれ落ちそうになってるってわけ」
「それってさ。お前の言葉で言うと──誠実じゃない、って思わないか?」
「選びすぎて、それでなにかが自然と零こぼれ落ちていくのって──」
「選ぶときは自分で選んだくせに、捨てるものは自分で選ばないで、成り行きにまかせてる、ってことだろ」
「選ぶっていうのは、捨てるっていうのと同じ意味なんだな……」
そして、日南の行動や思想について思うことになります。
「けどさお前、こうなるまえに、誰かに相談しなかったのか?」
だけどそのとき、何気ないトーンで問われたその言葉。
「いや、したけど」
言いながら、俺の頭には日南の顔が浮かんでいて。
「したのか、じゃあ不思議だな」
「不思議って、なにがだ?」
俺が問うと、水沢はやっぱり軽い口調で言う。
「だって……今回のすれ違いって恋愛としては初歩の初歩だから、聞けば誰でも、このままだとマズいことになるってわかりそうなもんなんだよ」
「……あのさ。ひとつ、聞いてもいいか」
「なに、改まって」
「菊池さんと俺の関係がマズいことになってたってこと……日南は気がついてなかったのか?」
「……質問の意図が、よくわからないのだけど」
「だから、そのままだよ。俺、日南に何度か状況を報告してたよな。そのときに、そう思わなかったのかって」
「正直に、答えてほしい」
「……はあ」
「もちろん気付いてたわよ。このままだと間違いなくこじれるだろう、って」
「……っ!」
「じゃあなんで、教えてくれなかったんだ?」
「付き合ったとはいえ、それで安泰ってことはないでしょ? どうせいつか喧嘩は来るわけだし」
「だからって、わざわざそのきっかけを放置することは……」
「そこからこじれて別れるところまでいくのが一番避けるべき結果よね。だとしたら最初の喧嘩はある意味練習。原因がはっきりしていて解決しやすい、しかも実際のところは誤解で、なにもしてないパターンのほうがいいでしょ? なら簡単なもので早めに練習しておいたほうが効率がいいと思って、あえて放置したの」
そこにはあまりにも、『気持ち』に対する配慮がなさすぎる。
こいつのなかにあるのはいつも正しさだけだ。
機械のように論理的に物事を進めていく日南は、
ゲームのキャラクターを操作するかのようで、
人間らしさを捨て去っています。
ある意味、サイコパスやマキャベリストなんですけど^ー^
まぁ、友崎くんは出会う人に影響されますからね。
日南 葵がやはりそうであることが、俺にとってはとても歯がゆく、悲しかったのだ。
「お前の価値観を否定しているわけじゃないんだ」
そう。否定しているわけではない。
なぜなら俺はあの北与野駅での決別のあと。日南のそういう冷たく頑なな部分も含めて向き合い、関わっていくと決めたのだし、
そんな日南に『人生の楽しみ方』を教えると宣言したのも俺の意志だ。
だから日南が、俺と菊池さんとの関係にもその冷たい正しさを適用してしまうこと自体は、仕方ないとすら思っている。
それがいまの日南の価値観だということは、納得できていた。
「これ以上聞いてたら、俺はお前のやり方を、考え方を。本気で嫌いになってしまいそうなんだよ。……だから、いまはこれ以上聞きたくない」
日南がそういう考え方を持った人間であることはわかっている。理屈の上ではきちんと、理解している。
「お前のやり方が『正しい』ってことをわかってても、気持ちの上で、嫌いになってしまいそうなんだ」「ここでの会議、いったんなくさないか?」
俺の言葉に、日南は一瞬だけ目を丸くした。
「……どうして?」
日南にしては珍しい、俺の意図を確かめる質問。俺は言葉に噓が混じらないよう、思いを伝える。
「さっき言った、これ以上聞くと嫌いになってしまいそうで怖いってのが一つ。それからもう一つは──」
頭をよぎるのは、大切な恋人が悲しんでいた顔。
「菊池さんと一緒にいる時間を、増やしたいんだ」
菊池さんは、真逆であるといいます。
みみみとも一緒に帰るのもやめました。
大切なものを少しずつ手放しているような感覚とも書かれています。
「ブレーンは自分の世界を広げていって、菊池さんは……人の世界を観察してる、って感じする」
「……おお」
言われて、俺はつい感心してしまった。世界を広げる人と、世界を観察する人。
「でもさ……それって相性いいってことにもなるんじゃないの? 恋人同士がお互いの持ってないものを持ち合ってる、ってことなんだし。旧校章を持つべき二人! って感じする」
「たしかに菊池さんって、友崎以外と遊んだりしてるの、あんまり見ないもんね」
「……そうなんだよな」
俺は実感とともに頷く。
日南ひなみに人生の攻略方法を教えてもらって世界の見え方を変え、自分の世界を広げつづけている俺と、自分の好きなものに向き合い、元々住んでいる湖で自分を深めつづけている菊池さん。
それはやっぱり、ポポルと炎人の関係に近かった。
「俺も元々はアタファミばっかりやってる湖の出身だったけど……そこから出たんだよな」
「湖?」
菊池さんがインターネットに小説を投稿することになります。
私の知らない飛び方とポポルのテーマをあわせたような作品になるといいます。
アルシア(日南 葵)について書くといいます。
オフ会に日南がついていく理由について訊かれます。
また、旧校舎の校章を受け取るのは、日南と友崎くんのほうがふさわしいと思っているようです。
「友崎くんのなかで、日南さんは特別な人なんですか……?」
「……友崎くんは私を選んでくれた、ってことはわかってるんですけど……」
「友崎くんにとって、本当に、鍵と鍵穴のような存在って、日南さんだと思うから……」
「ちゃんと来てくれてよかったよ」
「……別に、約束したわけだし」
「人生攻略は休止って話だったけれど、対戦会には誘うのね」
「まあ……人生攻略とアタファミは関係ないからな」
「ふうん……」
「まあ、そうだな。あのまま会議を定期的に続けたら、嫌いになってたかもしれない」
「そんな嫌いになりかけの人を、なんでわざわざ対戦会に誘うのよ」
「たしかに俺は、お前の冷たい考え方とか、正しさばっかりで人の気持ちを考えない部分に関しては、いまでもどうかと思ってる」
「それだったら……」
「忘れたのか?」
「俺がお前に、人生の楽しさを教えるって言っただろ」その言葉に日南は、ぴくり、と目を丸めた。
「……本当にやりたいこと、ねえ」
日南は眉を上げながら俺を横目に見て。
「ほかのことを証明する気は……もうないのね」「……ほかのこと?」
「……たしか、あなたが『とある人』にアドバイスをもらって、人生を攻略していっていることまでは、伝えてあるのよね? あと、信号赤」
「うおぉ!?」
「えーと、そうだな。人生を攻略していっていることまでは、伝えてある」
「だったら正直……風香ちゃんなら、もうその誰かが私であるってことまでは、勘付いててもおかしくないわね。確信まではいかなくても」
「まあ菊池さんは、たぶんここ二人は普通の関係ではないだろうなって、勘付いてるっぽいからな。……となれば、あるかもな」
「別に教えていいわよ。そもそもいままでも、バレたら絶対にダメってわけでもなかったし」
「そうなのか?」
聞き返すと、日南はさらりと言葉を続ける。
「クラスのリア充トップカーストが、クラスに馴染めない男子生徒にアドバイスして、クラスに馴染む手助けをしていた。そしてそれが見事成功した。これって別に、私の評判を下げるようなことじゃないでしょ?」
「それは……たしかに」
「しかもその男子生徒が、文化祭で演劇の中核になってクラスを引っ張って大成功、その後その脚本を書いた美少女と付き合って、果てにはなんかアタファミ日本一らしくてプロゲーマーになるとか言い出してる。ここまで行くと逆に私の評判が上がる可能性すらあるわね」
俺は頷きつつも、改めてこいつの人生攻略法の正しさに感服する。だってそんなところまで、半年ちょっとでいけてしまったんだもんな。
「っていうか実際、そこまで持っていったのはお前のおかげだからな。評判が上がってしかるべきだ」
「……ふうん」
「それじゃあ、話してもいいんだな?」
「ええ。構わないわ。……けど」
「よりにもよって──風香ちゃん、なのね」「……なんだ、それ?」
「あの子は私のことを……探ってるみたいだったから」
オフ会ではプロの足軽さんとの試合で勝率が下がっていることを驚かれます。
友崎くんは対戦ゲームで使用するキャラクターを変えたのです。
「うーん、やっぱりnanashiくんって、頭のネジが飛んでるよね」
「そうですかね。けど……自分なりには考えがあって」
「そっか。まあ、どういう理屈がそこにあるのかまではわからないけど、最終的な理由はわかるよ」
「……そうですか?」
「ただ単純に──そのほうが強くなれると思ったんだよね」
「……やめたのね、ファウンド」
「そうだな」
「せっかくそろそろ追いつけそうだと思ってたのに……本当に厄介な男ね、nanashiは」
「そんなに大げさに言うことか?」
「……どうして、このタイミングで変えたの?」
「まあいろいろあるけど……ファウンドだと読み合いが多くなって、実力が近い相手だと安定しないと思ったのが一つ。お前との読み合いは得意だったから気づかなかったけど、たぶんいまのプレイスタイルだと、今後大事な大会で運負けする相手も出てくるんじゃないかと思った」
「大事な大会……ね」
「本気、ってことね。……プロゲーマーになるって」
「もちろん。本気だ」
「だろ? 全敗したけど、毎回ワンストック差くらいで……このまま立ち回りを洗練させれば、そのぶん結果が伸びていく感じだったな」
俺は手応えを感じながら言う。
負けが込んだからといって、それは退化しているわけではない。
むしろ強くなるために一時的になにかを失わなければならないことは、勝負の世界には往々にしてあるのだ。
「お前はさ……なんでそこまで俺に……いや、nanashiにこだわるんだ?」
「取り戻すんじゃなくてな、俺は一刻も早く、元の実力を大きく上回るんだよ」
「……お前、ホントにアタファミ好きだよな」
「……私は、あなたのプレイを模倣して、実力を上げていってたのよ」
「一つ一つ分析して、同じように練習して、やれることを増やして」
「それは、俺が一番よく知ってる。ほかの誰だれよりもな」
「……キャラを変えられると、こっちはすごく困る」
「……まあ、それは我慢しろ」
対応に困りながら言う。
たしかに日南は俺のファウンドを真似まねて、ここまで上う手まくなった。だから、俺がファウンドをやめてしまえば、日南の実力はその段階の俺で止まるだろう。
正確に言えば、その段階の俺の無駄な動きをそぎ落とし、操作精度を少し上げたレベルで、だろうか。
けど。
だからといって、ここまでいつもの調子が狂うものだろうか。
「ていうか、お前もジャックを使い始めればいいだろ。いいぞ~ジャックは」
俺の提案に、日南ひなみはあからさまにため息をついた。
「……あのね、残念ながら私はまた一からキャラを育てて完成させていくだけの時間はないし、それは無理。……っていうかあなたこそ、彼女もできて受験もあって、そんなことしてる時間あるの?」
「さあな。時間がなくても自信はある」
「……あっそ」
「人生攻略を休止して、メインキャラクターも変えて……そろそろ、私といる意味はないのかもしれないわね」「なんだ、それ?」
日南がらしくない卑屈なことを言っている。
「俺はまだお前から人生において学ぶべきことはあると思ってるし、お前に人生の楽しみ方を教えるっていう大事なミッションが残ってるんだ。お前といる意味がないなんてとんでもない」
俺は堂々と言うが、日南は表情を変えず、疑うようにこちらを見ていた。
「人生の楽しみ方……ね」
「……それが、私の救いになるとでも思ってるの?」
「ああ。それが俺のやりたいことなんだ」
レナちゃんと日南の会話です。
日南は、人間を改造するのが趣味ですけど、
だれかにコントロールされるのは嫌なようです^ー^
「人には踏み入るけど、自分は踏み入らせない、って感じするもん」
「あ、それ当たってるかもです」
日南が片眉を上げると、レナちゃんはじっとその表情を値踏みするように見つめた。
「誰かに自分を変えられちゃうのがいやなんでしょ?」
すると日南はぴくり、とまぶたを動かす。
「……そうですね。自分のことはあくまで、自分で操作したいなって思ってます」
「だよね」
「──Aoiちゃんは、臆病なんだ?」
「臆病……というか、誰かにまかせたら、それが間違ってるかもしれないじゃないですか」
「そうだけどね? 私はそういうのも含めて、楽しみたいってタイプなんだあ」
「私は間違ったほうへ進みたくないから……その辺の考え方が違うのかもですね?」
「だねえ」
レナちゃんはご機嫌に頷くと、目を溶かすように細めながら、見透かすように口角を上げる。
「わたし、ちょっとだけAoiちゃんのことがわかってきたかも」
「あはは、それはなによりです」
日南は柔らかく笑うが、レナちゃんはまだじっと、日南のことを見つめていた。
「うん。Aoiちゃんってなんかちょっと、私に似てるのかも」
「え。そうですか? レナさんと私が似てる?」
明るく問い返す日南に、レナちゃんは楽しそうに口角を上げる。
「私はね。誰だれかに認めてほしいんだ。自分には価値があって、求められてる存在なんだって」
「あー……それはそんな感じしますね」
「でしょ?」
「たぶんAoiちゃんは、私よりも現実的で、欲張りだから──」
言いながら、レナちゃんは不意に手を伸ばし、日南の頰にその細い指先で触れた。
「誰かに、ってだけじゃ満足できないんだよね」
それはなにか官能的な声のトーンで。けれど、言っていることは俺にとって興味深いことで。
「……そうですね。誰かがいいって言ってくれるから、それで自分をよしとするなんて、ただの依存じゃないですか」
するとレナちゃんは納得するように笑う。
「ほらね? やっぱり」
そしてレナちゃんはうっとり見とれるように指先を離して、ゆっくりと日南の肩に触れた。
「私──そういう私に似てる空っぽな女の子、好きだよ?」
蠱惑的に上げられた口元、落ち着きのある視線。そこにはやっぱり、危険な香りが漂っていて。
日南もそれと同じくらいかそれ以上に余裕のある笑みを返すと、
「ありがとうございます。私もそんな自分が、嫌いじゃないですよ」
ゲームにしても、すべての行動を考えて行動していると日南はいいます。
勘ではなくです。
「だから……たぶんAoiさんは、恋愛でも自分以外の誰かに踏み入られて、自分が積み重ねていった理由を壊されるのが嫌いやなんだろうな、って」
「たぶん、そこがAoiさんの強さの理由だね。すべての行動に理由があって、理由が見つからないときは決して動かず、様子を見る。そして自分が知っている状況になったとき、その状況において正しいと知っている行動を取っていく」
なのにその言葉はパーフェクトヒロインの仮面の内側──いや、人間・日南葵の本性を語っているようにすら聞こえたのだ。
足軽さんの目には、こいつの裏の顔である完璧主義な日南葵の姿は──いや、それどころか、オンラインレート日本二位のNO NAMEであることすら、映っていないはずなのに。
そうして主導権を握るとともに、語りやすいところへ話題を持っていく。
そんな感じで日南についての話題は終わってしまったけど、そこで語られたいくつかの言葉は真相を解き明かす手がかりになる気がして。
俺の知っている裏の顔と、別の人から映る日南の特異性。それらが交差する地点に、俺の知りたいものがあるような感覚があったのだ。
人と人とが付き合うことについて語ります。
俺っちのブログにも書いてありますけど、
どれだけ、そいつに自分の時間を割けるかどうかです。
自分が友だちだと思っていても、向こうが友だちだと思っていないことはありますが、
一緒に遊べば友だちだと思います^ー^
「えっとねぇ。私が思うのは……お互いに、束縛してもいいってことかな」
「束縛……」
「たしかに彼氏を作ると、そうなっちゃいますよねぇ。自分のやりたいことができなくなって、やりたくないこともやらなきゃいけなくなる、みたいな」
「あー! そうそうわかる! だからいまは私、あんまり彼氏っていらないんだよね~」
「あはは、私もです」
日南が自分にとっての彼氏という存在について語るのは初めて見たな。
「そういうふうに、『他人』には踏み入れない『個人』の領域に足を踏み入れて、お互いに人生の責任を少しだけ預け合えるようになる。……もし友達でなく恋人になる理由があるとしたら、そこなんじゃないかな」
「なんというか……僕は付き合ったんだとしても、お互いにやりたいことがあるなら、それを第一に尊重したいな、って思ってるかもしれないです」
オンラインレート一位を維持し続けてきた俺は、その『個人は個人で結果は自己責任』という考え方を、ひとときたりとも見失ったことはなかった。
超個人主義の人生観について語ります。
「nanashiくんはいままで、誰だれかに対して尊敬や好意や感謝はあったとしても、自分以外の人間に深く入れ込んだことは、ひょっとすると、ないのかもしれない」
「……そうかもしれないです」
「いまの彼女を含めて、俺は誰かに自分の責任を預けたことは、ないんだと思います」
「だとしたら、nanashiくんはそもそも──恋愛に向いてないのかもしれないね」
遊びに行ったり、家まで送ったり、朝一緒に登校したり。
それは恋人らしい行動だったけれど、友達のままでもやろうと思えばできたことだろう。
それを水沢は、〝形式〟だと言った。
──俺は自分のなかに潜んでいた感情を自覚しながら、菊池さんの姿を思い浮かべる。
未来へと続くドアに向かって道を歩んでいる菊池さんと俺は、隣を歩くパートナーにはなれたのかもしれない。
もしくは同じ方向を見て協力しあう、同志にもなれるのかもしれない。
けれど、それでもあくまで歩いている道自体は二本の平行線で、手を振ろうと、どれだけ言葉や気持ちを重ねようと──俺のなかでその道は、決して交わらない一人一人の道だった。
きっとその先にあるドアも、それぞれに一つずつ用意されていて。
そしてこの結論は、俺のなかで決して変わらないという確信もあった。
オフ会の帰りの電車にて。
「……なあ、日南」
「そろそろなにか言ってくると思った」
「おい」
「お前はさっきの話、どう思う?」
「別に。人は人、自分は自分なんて、ゲームにおいて当然のことでしょ。自分がそうであることに、ショックを受ける必要なんてない」
「そもそも、それが特殊なことかのように語られてたのが最悪だったわ。まあ私はあの場でそんなことを言うわけにはいかなかったけれど、個人が個人として生きる。責任を誰だれにも転嫁せず、きちんと自分で抱かかえて前に進む。こんなに美しいことがある? ……なにも、否定される謂われなんて、ない」
どこか感情的な口調。けれどそれは迷いなく断定するような強さを湛えていて、少し気を抜けば、そこに体重を預けてしまいそうになるほどの。
「はは……やっぱお前、強キャラだわ」
言うと日南は一瞬だけ眉をひそめ、やがてまた当然のように。
「それはあなたが弱キャラなだけ。人生を一人で生きていくことができないなんて、それこそ努力と分析が足りないんじゃない?」
その言葉にまた俺は、つい安心して笑ってしまった。
「──お前は、変わらないな」俺が言うと、日南ひなみは一瞬だけ目を見開く。そして視線を窓の外に移し、肩口まで伸びている滑らかな髪の毛の先をつまんだ。
それは日南にしては珍しい挙動で、なんだか俺は最近、こいつの珍しいところを何度も見ているような気がしていた。
「そうね。──私は、変わらない」そうして毛先を離した日南の表情にはどこか決意のような色があって。さっきまでつままれていた毛の先はぱらぱらと落ち、ほかのものに混ざって、もうどこにあるかわからない。それはきっと、日南自身にも。
「けどさ……一人で生きるのって、寂しくないのかな」
俺がこの先のことを考えて不安を逃がすように言うと、日南はまた、目だけを動かして俺を見た。
「さあね。……けど、少なくとも」
「少なくとも?」
俺が聞き返すと、日南は決意のこもった表情で俺を見た。
それはあまりに強く、仮面のように人工的だったけれど、どうしてだろう。その表情は、日南の内側にある表情に思えた。
「私は、寂しくても平気」
日南と別れた数十分後、菊池さんが書いた小説を読みます。
そこには、アリシア……つまり、日南を題材にした小説が書かれていました。
そして、他人の長所を取り入れてコピーするという日南の特性までが描かれていたのです。
菊池さんの裏の顔や思想については話してはいません。
菊池さんは自力で日南の本質にたどり着いたのです。
つまりは、究極の器用貧乏。──それがアルシアだった。
「やっぱり……これって」
その名前のことがあったから、というのもあったけれど。
そうでなくとも俺は同じ結論に至っていただろう。
あらゆる分野で結果を出すために。
その道のトッププレイヤーのやり方をとことん真似まねして、シンプルな努力の量だけで抜きん出ることによって、自分の正しさを証明つづける。
アタファミではnanashiである俺の真似をしていたように、おそらくは勉強でも部活でも人間関係でも、なにかの手本をもとにして、それが血肉となるまで真似をしつづけ、知識が記憶にこびりつき、脳が反射としてその動きを習得するまで反復練習をしつづけてきたであろう日南 葵。それはまさに、この物語のなかのアルシアの在り方だった。
俺は鏡を見つめ、笑顔を作っては元に戻しを繰り返していた。
日南にもらった武器。きっと日南がリア充としての『純血』から血を借りて、真似をして。その結果に得たスキルを、俺にも教えてくれた。
それは俺にとっては自分の世界を広げる『ポポル』であるためのスキルの一つで、人と関係を作るきっかけを作るための仮面だった。
得られるとしたら『こうすればうまくいく』という正しい知識の積み重ねだけだった。
あらゆることで一位になって。
けどそこに『やりたいこと』を持っていない日南 葵。
あいつが目指している最後の目標は、一体どこなのだろうか。
菊池さんと通話をします。
菊池さんは、日南は優勝だとか一位とかそういうわかりやすい価値を求めているだとか、
世間で価値を認められていることに重きを置いているといいます。
そして、2人のデートの最中に日南の家族と会います。
そして、家族ですらも仮面をつけて話していることに驚きます。
「友崎くんって、素敵なお店をたくさん知っていますよね」
「うん? そう?」
「はい! だって、大宮の喫茶店もそうですし、さっきのお店もとっても素敵でした!」
「あ……」
「友崎くんについていくと、いっつも新しく素敵なものが知れるので、私はとっても楽しいです」
「こういうお店って、どうやって見つけるんですか?」
「えーと、今日のお店は……何回か、日南と来たことがあって、それで」
「……日南、さん」
「そ、そっか、だからさっき……」
「うん……そうだね」
「えーっと、じゃあ大宮のお店は……」
「あー……」
「えーと……そこは日南と行ったこと自体はないんだけど、教えてくれたのは……日南だな」
「そ、そうなんですね……?」
「前に、私のバイト先にも……二人だけで来てましたもんね」
「あ……」
「あの頃って……友崎くんがまだ、みんなと仲良くなってない頃でしたよね……」
「あのさ、菊池さん」
だから俺は菊池さんを、すべてが詰まったその場所へ誘おうと思っていた。
「明日の朝、来てほしいところがあるんだ」
「私……友崎くんのことが、もっと知りたいです……」
「……俺のこと?」
菊池さんは頷うなずく。
「なんだか私、友崎くんと付き合ってるのに、友崎くんのこと、なにも知らないような気がして……」
「そ、そんなこと……」
菊池さんは、うつむき気味に首を横に振る。
「いろいろなことを教えてもらったけど、全部ただ聞いただけで……過ごした時間も、出会ってからの時間もたぶん、その……負けてて」
なにかに対抗するように言う菊池さんは、不器用ながら、俺の目を見つめていて。
「私、友崎くんのこと、一番知ってる人になりたいんです……」
菊池さんを家に呼び、友崎くんが好きなものについて知りたいといいます。
それでアタックファミリーズをやることになります。
「アンディ作品のこと──知ろうとしてくれたから」
「このゲーム全体でだと、どのくらい練習したんですか?」
「えーどうだろ。……時間で言ったら、一万時間はやってるかな?」
「なんて言うか……俺は自分の選択とか、判断みたいなものをすごく信じてて、だから個人は個人だって思ってて……」
「……はい」
「でもそれは……いま菊池さんが言ったみたいに、俺がゲーマーだからなんだよ」
「……自分で目標に向かって努力して、自分で結果を出すから、ってことですよね?」
「え」
「うん。そうだけど……よくわかったね?」
「友崎くんのことは……一人でいるときも、たくさん考えてるから」
「友崎くんが個人でいたいのって……きっと、恋人同士って関係になっても、変わらないんですよね?」
「……っ!」
「……いまのところは、そうなんだ」
「そっか……」
「たぶん俺は……誰かに好意とか感謝はあっても、自分以外の人間に深く入れ込んだことはないのかもしれなくて……」
「だから、少し不安っていうか……俺は個人でしか生きることができなくて……誰かと本当の意味でつながれることはないのかな、って考えると、怖くもあって」
「それって……とっても、寂さびしいことですよね」
その場に落とすように言う。
「やっぱり……そうなのかな。これじゃ、俺はずっと寂しいままで……」
俺が自嘲するように言いかけると、菊池さんは小さく、唇を嚙かんだ。
「それも……そうなんですけど」
そして菊池さんは、目にうっすらと涙を浮かべながら、寂しく笑った。
「寂しいのは……私もです」
「そうだよね、ごめん」
「ううん」
「──きっと、日南さんも、同じってことですよね」
「え……」
「自分で目標に向かって努力して、自分で結果を出す人って、日南さんもですよね?」
その視線には、鋭さと不安が同居していて。
それは日南の、もしくは俺たちの、本質を突いている気がした。
「……そうだね。あいつも、そこは同じだと思うけど……」
そして、菊池さんの小説がまた投稿されます。
それは、まるで日南の指導を追体験しているかのようで……。
そして、菊池さんに取材されていることに気づきます。
リブラはあらゆる血を持ちなんにでもなれるため物事に執着がなく、変化することに抵抗のない少年だった。
だから一つの種族のスキルを自分のできるところまで極めても、それを捨てることに迷いがなかった。
田舎町からアルシアについていき、そこから雑種の転校生として生き抜くという選択すら、
自分の運命を大きく変えるものだったのにもかかわらず、まるで生き抜くことそのものをゲームのように捉え、楽しんでいた。
そしてあるとき、リブラはアルシアにこんなことを独白する。
自分だけが純混血で、だからみんなとは種族が違っていたリブラ。
──自分は個人でしか生きることができなくて、誰かと本当の意味でつながれることは、ないのかもしれない、と。
瞬間、俺のなかの混乱や驚きがすべて、寒気と確信に変わるのがわかった。
だって、その一言は。
その、葛藤は。
──俺があのとき菊池さんに告白した、俺という人間の業だったから。
──役者として、自らの闇やみそのものを演じたのだ。
キーとなったセリフ。
『私はすべてを持っているわ──。けど──だからこそ、なにもないの』。
それはおそらく日南にとって、自分でも自覚しているかどうか怪しいくらいにあいつの心の芯の近い部分に巣くっている、闇のようなものだろう。
それを具体的に突きつけられ、懺悔するようなセリフとして生徒たちの前で言うことを強制された日南 葵は、どれだけ心を揺さぶられただろうか。
「……っ」
どうして、気がつかなかったのだろう。
そして、第二被服室で日南から指導を受けていたことを菊池さんに話します。
オフ会から始まったこと。
人生に本気で向き合うように指導されたこと。
そして自分のことも好きになれたこと。
そして人生の楽しさを日南に教えようということ。
「それは……友崎くんにとって、これ以上ないくらい、大切な存在ですよね」
「……うん」
「だからやっぱり、特別なんです……私なんかよりも」
「そ、そんなこと……」
「だって日南さんは、友崎くんの世界の色を変える魔法が使えるだけじゃなくて、それこそ勉強や部活にも励んで、結果を残していかないといけないと思うんです」
「そういう、わかりやすい価値のあると思えるものにしか時間を使わないはずなんです」
「なのに──。どうして誰かを変えるための、魔法を使おうと思ったんでしょう?」
日南が主人公を改造しようとする理由……。
菊池さんですら理解できなかったのです。
まぁ、読者のほとんどは気づいていますけどね。
そして、主人公は、ストイックで日南と同じ個人主義といえど、
血潮がたぎったガイで、鉄仮面の日南とは違います。
思わず涙が出そうになりました。
「──どうして友崎くんは、日南さんのことをそこまで知ろうとするんですか?」
「……っ!」
「私は思うんです。アルシアはきっと、自分の血がなくて、したいことがなくて。だから見てる世界が昔の私や友崎くんみたいに……モノクロなんです。正解ばかりを求めて、自分が、自分の気持ちでこうしたいみたいなものを、なにも持ってなくて」
「……うん」
物語を使って深掘りするように。俺を、導くように。
「友崎くんはそんな女の子を見て、どう思ってるんですか?」
「俺は……たぶん、日南の世界がモノクロなのが、嫌いやなんだ」
「うん……」
「……俺はたぶん、あいつが、日南が大切な存在だからこそ。あいつにいままで、数え切れないほど、大切なものをもらったからこそ──あいつがそんな、寂しい思いをするのが嫌なんだ」
「それは……日南さんが、世界に色をつけてくれた人……だからですか?」
「友崎くんのことを……この世界でもポポルにしてくれた人なんですよね?」
菊池さんは、怯えながら。
「この世界を……、カラフルにしてくれた人なんですよね?」
きっと、そうしなければいけないから。
動機を問う言葉を、俺に投げかけつづけた。
「あいつは、自分でも知らないうちに、そんなつもりもないうちに、世界に素敵すぎる魔法を使ってて……。自分がそんなものを与えたってことにも気付いてなくて……俺が日南からもらったものをどれだけ大切に思ってて、俺が日南にどれだけ感謝してるかすら、あいつはわかってないんだ」
高校生で、ここまで人を尊重し、尊敬することができるでしょうか。
「……はい。そうだと、思います……」
震える声で言いながら、菊池さんは一粒の大きな涙を零した。
──なのに。
「だって……二人は同じで……。二人とも、個人で生きてるから……!」
「そう……だからあいつは、俺が感謝したって、自分はなにもしてないって言うんだ。それは自分がやりたくてやったことだからって。自分の意志でした選択だからって。……けど、俺はその気持ちが、誰だれよりもよくわかるんだよ! ……だって俺もどうしようもないくらいにゲーマーで、個人主義で……、そうやってアタファミをやってきたから」「感謝しても伝わらない。受け取ってもらえない。……だから、俺はさ」
視界が少しずつ、涙で滲にじんでいった。
「俺の意志で、日南の世界をカラフルにしたい。
あいつの見てる世界をカラフルにして、人生っていうゲームを楽しんでもらいたい」「俺が、そうしたいんだ」
「……やっぱり、そうなんですね」
そして顔を上げると、菊池さんは、涙をぼろぼろ流していた。
「だから日南さんは……友崎くんにとって、特別な人……っ、なんです」
「ごめんなさい……話を聞いていて、そんな素敵で、綺麗な関係ってあるんだなあって眩しくなって、嬉しくて、涙が出てきて」「同じゲームを愛して、お互いに尊敬し合って、自分のためにしたことで、相手に大切なものを与えて、だからそれを返すために……友崎くんもがんばろうと思ってる……そんなのあまりに理想の関係すぎて、素敵で……」
「……だからっ! 私の入る余地なんて、少しもない……っ!」
「俺はさ……菊池さんのことが好きなんだ」
「……っ!」
「その気持ちに噓はなくてさ……こうして日南に対する大切な気持ちを自覚してからも、やっぱり菊池さんのことは好きなんだって、思えてる自分がいる。なんていうか俺はある意味、それに安心してて」
「……うん」
菊池さんも涙を浮かべながら、真剣な表情で、それを聞いてくれている。
「けどさ……日南に人生の楽しさを教えたい、俺があいつの世界をカラフルにしたいって気持ちは──」
「──俺のなかではきっと、恋愛とか、そういう気持ちよりも、大事なことなんだ」
「あいつを恋人にしたいとか、そういう意味でもなくてさ。たぶん、恩人とか同志とか、仲間とか……そういう方向で、あいつのことは大切なんだと思う」
「だから、友崎くん。もしも、友崎くんの荷物が自分の手に余ってしまって、なにかを捨てないといけないんだとしたら──」
「手放すものに、私のことを選んでくれても、いいですからね」
水沢はいいます。
校章なんて形式にすぎないと。
「──運命の旧校章なんて、別にもともとは誰かがつけてたお古の鉄くずだぞ? そんなんに相応しいもくそもないからな?」
友崎くんは弱い人の気持ちがわからないといいます。
薄々感づいているかと思いますが、
この作品の主人公はとても器用で優秀な人間です。
使用するキャラクターを変えてみたり、自分自身の振る舞いを変えてみたり……。
変化をすることに恐れをしない人間なんです。
自分は弱キャラだと思っていたら強キャラだったんですね。
そして、主人公は人間関係を切ることにします。
クラスメイト……友だちです。
俺にとって大切なものは、もしくは誠実に向き合いたいものはきっと、アタファミを人生にしたいという道と、日南ひなみに人生の楽しさを教えたいという思いと──そして、菊池さんと恋人同士でいたいという関係だけで。
たしかにこの世界は日南に教えてもらって自分の意志で得たものだったけど、俺はその一部を失っても、きっと前に進んでいける。新しい景色を見つけていける。
だって、世界はこの学校だけではないのだから。
だから俺は、大切なもののために、荷物をそっと置いていくことを選択した。
自らすくい上げた砂を指と指のあいだからさらさらと零していき、粒の大きいものだけを残していく。
けど、俺が欲しいものはきっと、その大きな粒だけで。
その大きな何粒かを大事にすることがきっと、俺の人生のプレイスタイルなのだと思えていたのだ。
そんな行動をしていると、みみみに声をかけられます。
「……俺は、いままでずっとひとりぼっちで……」
「……自分だけで生きてきたから、きちんと人とつながる方法がわからなくて」
「……うん」
「……俺はさ、自分で菊池さんを選んだんだ。私は相応しくないって言う菊池さんに、無理やり理由を与えて。理想なんてどうでもいい、俺が菊池さんがいいんだ、って……」
「だからちゃんと、向き合わないといけないのに……菊池さんに寂しい思いばっかりさせて」
「──自分の手に持てるもの以外は、みんなとの時間は、置いていくことにしたんだ」
「……そっか」
「こないだ菊池さんと偶然会って、話したんだけどね。……私も、菊池さんも、一緒だったの」「……友崎のこと、好きな理由」
「え……」
「ちゃんとがんばって、自分を変えて、どんどん自分の世界を広げていって。……そんなブレーンの強くて、真っ直ぐで、キラキラしてるところが、二人とも好きなの」
「世界を広げて……」
「いまの友崎がしてるのってさ。世界を広げるのをやめて、新しいことに向かうのをやめて。菊池さんを嫉妬させないように、自分の世界を狭めて……」
「それって──私と菊池さんが好きな友崎の好きなところを、変えちゃおうとしてるってことなんだよ?」
そして、菊池さんは、友崎くんがいいと言います。
「友崎くんは、半年以上もかけて自分を変えて、世界を広げて……景色がカラフルになっていったのに。それを捨ててまで……私のために、変わろうとしてくれたんですよね?」
「友崎くんは──ポポルである自分を捨ててしまえるくらいに『ポポル』なんだなあって」
「だから友崎くん。無理に自分を変えようとしないでください」
「私は、私のために大切な自分を変えようとしてくれた、その事実だけで、十分なんです」
川が涼しくそそぐ音。名前も知らない虫の鳴き声。通り過ぎていく、たぶんあのときとは違う、ヘッドライトの光。
見える聞こえるなにもかもがどうでもよく感じた。こうしているだけで、いままでのすれ違いや不安。いろんなものが、二人のゼロ距離に溶け合って消えていくようで。
だからいつまででも、こうしていられる気がした。
「……ごめん、意地悪を言った。実は……俺はもう、その答えを知ってるんだ」
「え?」
戸惑う菊池さんに、俺はいたずらっぽく笑みを見せる。
俺はいろいろな人から恋愛についての話を聞いて、いくつも大事なことを学んでいた。
不安は一つ一つ向き合うしかないし、付き合ったあとじゃないと話せないことは山ほどあるし、そもそも付き合うっていうのは、恋愛の最後の目標じゃないらしい。
そして、運命の旧校章も、どんな『特別』もきっと。
ただ単に〝形式〟を──いや、物語を積み重ねて生まれているんだということ。
だから。
「これはさ。ラブコメのアニメでも恋愛ゲームでもなくて──単に、人生なんだ」
だったらここは、この場所は。恋に惹ひかれ合った二人がたどり着いた攻略完了というゴール地点なんかじゃなくて。
俺たち二人にとっての、スタート地点なのだ。
「覚えてますか? 二人で一緒に見た、空に浮かぶ花火。心を溶かすみたいな輝きで、ずっと灰色だったはずの景色も、色とりどりに見えたんです」
「川が近くてちょっと蒸し暑かったけど、光を反射する水面はとってもきれいで。私、あんなカラフルな世界を見たの、生まれて初めてでした」
このセリフを読んでいるときに、TVアニメ『色づく世界の明日から』を思い出しました^ー^
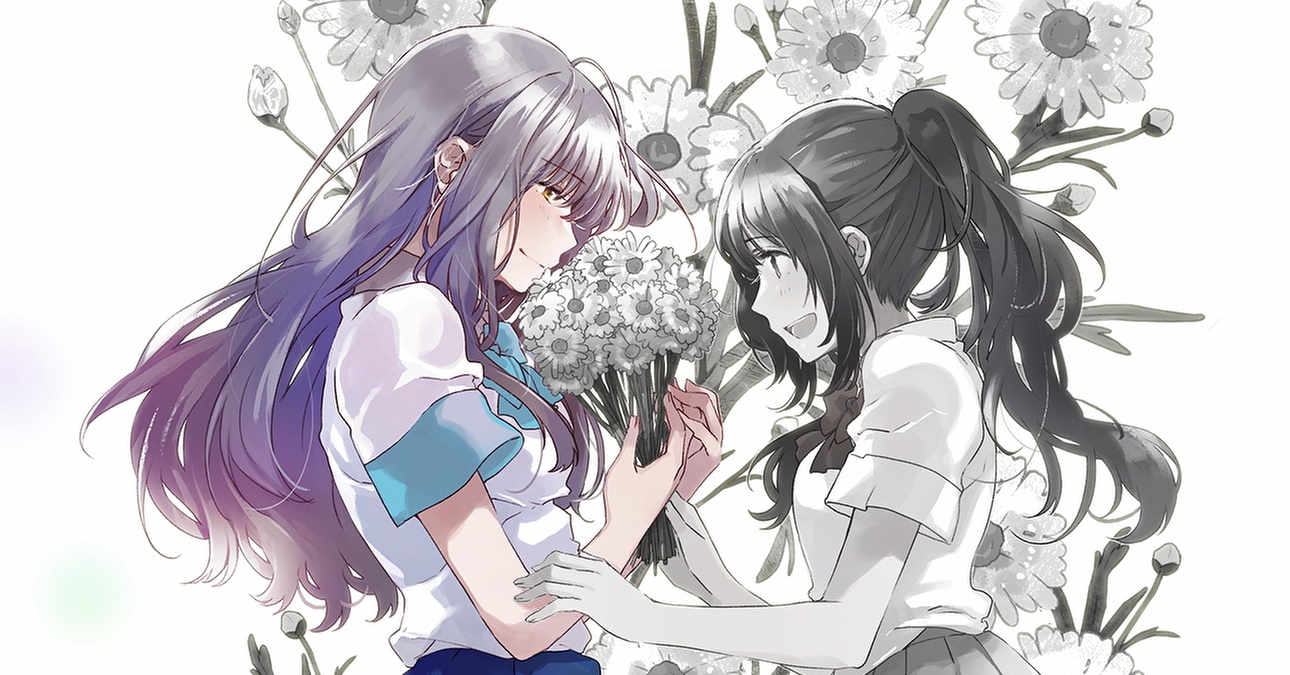
無事に三年生を贈る会を迎えます。
「旧校舎の旧校章。これってやっぱり……まるで友崎くんと日南さんのためにあるように思えませんか?」
「う……仕返し?」
俺が話した日南ひなみとの半年間。たしかに過ごした秘密の時間の多くは、この旧校章が使われていた時代の旧校舎にある、第二被服室で行われていて。
俺と日南にとってその場所は、その時間は。間違いなく特別だった。
何度も言われていた、俺と日南の特別性。そこに旧校舎と旧校章とまで来たら、たしかにそうあるべく作られたような、運命めいたものを感じてもおかしくはないだろう。
そして俺と日南がこの校章をつけて、もともとそれが使われていた校舎に二人で集まって。そんな光景が頭に浮かぶと──たしかにこの校章は、まるで最初からそのためにあったかのようにも思えて。
きっとそれ自体にはなんの力もない校章。ただの鉄の塊に物語がつけられて、そこに誰かが持つ意味や、受け継ぐ理由を見出だして。
「これって言っちゃえばただの古い校章だけど……みんながそれを信じたから──いつの間にかこの錆も、汚れも。本当に特別になっていったんだよね」
それはきっと、積み重ねた物語の力で。
「だから……俺たちの関係も、きっと」
そこまで言うと菊池さんも嬉しそうに頷いて、その校章をじっと眺めた。
そして愛おしいものを撫なでるように、その傷を、錆を。優しく指でなぞる。
「私たちのすれ違いも、矛む盾じゆんもいつか……この傷みたいに」
人間操縦、人間を改造したがる日南の気持ちに気づきます。
日南は幼児的万能感に浸っているのかな^ー^
「お前が言う『キャラ変』ってのはさ……」
「俺を変える、って意味じゃなかったんだよな」
「──お前だったんだ」
俺がそう言い切ると、日南は目を大きく見開き、結んでいた唇くちびるが、少しだけ開いた。
「お前の言うキャラ変っていうのは、プレイヤーとしての日南葵が──操作するキャラクターを変えるって意味だったんだよな」
「人生を攻略するキャラを変えても──友崎 文也やという弱キャラを使っても、同じ結果が再現できるってことを、証明したかったんだよな」
「自分のやり方が『正しい』ということを証明する──ただ、そのために」
それはこいつの行動理念や価値観をもとにひとつひとつ丁寧につなぎ合わせれば、単純な話だった。
日南葵は正しさだけを信じて、それを拠り所に生きている。
だから、自分のやり方でわかりやすい結果を残すことでその正しさを証明し、そこに価値を見出だすことを繰り返し、毎日を生きてきた。
勉強、部活、人間関係、恋愛。
すべてを分析して『攻略』していき、一位と呼べるところまで辿り着くことで、その価値に安寧を感じる。
正しければ正しいほど自分に価値が生まれて、その証明に躍起になっていって。
正しければ正しいほど安心できて、また新しい正しさを求めていく。
繰り返していくうちに、やがてこいつはこんな発想に至ったんだろう。
この『攻略法』は──自分以外が使ってもほんとうに、正しいのだろうか、と。
俺は『再現性』という言葉を繰り返し使っていたこいつのことを思い出す。
環境を変えても同じやり方で同じ結果が出れば再現性が高く、それはより正しいと言える。
科学だろうが数学だろうが、物事の正しさを論理的に担保できるのは、再現性があるかどうかしかない。
それを人生でも使うなんて、実に日南らしい正しさの証明だろう。
「お前が俺に見える景色が変わる魔法を使ってたのは、俺を救うためでも、俺に勝ちたかったからでもなくてさ」
そして俺は──それこそ、前提から結論を証明するように。
「お前が考えた『人生』というゲームの攻略法の正しさを、証明したかっただけなんだ」
「……さすが、nanashiね」
そして、日南は否定しなかった。
「やっぱり……そうなんだな」
戸惑いを隠すようなトーンで言う日南の言葉に、俺は悲しくなってしまう。
「たかが半年余りでここまでこれたんだ、お前のやり方は正しいよ。けど、もう充分だろ」
俺はこれまでこいつと過ごしてきた時間のすべてが少しずつ、モノクロになっていくような感覚を覚えながら。
「そんな、人を利用するような──俺の人生すらも利用するようなやり方で、自分の正しさを証明しようとするのは、もういいだろ」
溢れ出す感情を隠さずに言うと、日南はさすがに後ろめたいのか、俺から目を逸そらし、斜め下を見た。
「さすがに、怒ったでしょうね」
孤独とはつまり、自己責任のことで。
誰かとつながるというのはつまり、人と責任を預け合うことで。
そして依存のような関係になってしまうことこそが、きっと最も軽薄で愚かしい。
なんならそれこそ、無責任と言うべきものだろう。
俺はきっと、自分のなかで自分だけを。
いや、もしくは世界のほうを──自分とは別の檻の中に閉じ込めることで、人生を生き抜いていたのだ。
日南は正しさだけを信じていて、それ以外のすべてを──それこそきっと、自分すらも信じていない。
一位や優勝というわかりやすい形での正解にしか意味を見み出いだしていないし、そこに自分のやりたいことという基準が存在していない。
正しさを証明することそのものが目的になっていて、俺という存在すら、正しさを表明するための『キャラクター』として使っていた。
だからあいつは正しいという理由がない行動を取ることができないし、間違ったものに対する頑なな拒絶があった。
それはある側面では極端な自己責任思想であって、だからこそ自分が操作するもの以外のすべてに期待しないし、他者を自分の世界に入れることもなかった。
俺とあいつは、根拠のない自信の有無という違いはあれど、自分は自分で他者は他者という、個人競技における原理原則に則って。
自らの努力による結果をなによりも信じて。アタファミ、あるいは部活や勉強──つまりは人生という名のゲームと向き合い、そこで戦ってきた。
けど、それはきっとあくまで二人とも、個人競技としてだったのだ。
俺がキャラクターで。あいつがプレイヤーで。
俺が気持ちで動く人間で。あいつが理屈で動く人間で。
俺がもしかすると強キャラで。──あいつがもしかするとほんとうは、弱キャラで。
同類だと思っていた俺とあいつは、実はゲーマーであるということ以外、なにもかもが違っていて。
けれどその一点だけで、なにもかもがつながっていて。
そんな俺とあいつにはきっと、たった一つ。
そう。たったもう一つだけ、共通点があるのだと気がついていた。
──俺と、そして日南 葵は。
──きっとほんとうの意味で、ひとりぼっちなのだ。
『弱キャラ友崎くん』は、1巻、3巻、7巻、8巻……そして、今回の9巻を読めば問題ないです。
アニメは、3巻までの内容になると思うので広告プロモーションと考えればいいのかもしれませんが、
見る必要はありません^ー^
アニメ放送中に新刊が出たのは良かったですけど。






