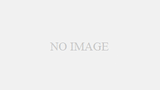???「弟子にしてやろうか?」
全てを教え、全てを教わる。
これが「指導」というものだ。
教えるのが上手で、教わるのが上手であれば、指導はうまくいくはずだ。
現代社会では、指導を履き違えている輩がごまんといる。
「目で見て覚えろ。俺は教える気はないからな」とパワハラされたり、
ときには「仕事ってのは『職人』なんですよ。技を盗むってのが重要なんですね。まぁ、私は教えませんが^ー^」と、
教えないどころか小馬鹿にされたりする。
「俺がやったほうがはやい」と端っから教えないやつもいる。
教育現場では、教えるのではなく、
授業そのものを終わらせることに重きを置いている教師もいるのである。
教えるというのは、とても難しいのだ。
その道のプロや第一人者の指導というのは、
素人ではわからないことが多々ある。
これは、指導される側が「教わるレベル」に達していないからだ。
努力をして指導者の言葉や思想、概念が理解できるようになる必要がある。
習熟していないと、教えるほうも「やる気がないやつだ」と受け止めるだろう。
そういったばあいは指導ができない。
導けない。
指導者に求心力は必要ない。
物事の経験者の説教は、言葉には形容しがたいものがあるかもしれないが、
指導に限界はないのだ。
つまり、教えるのが上手で、教わる方も上手であるのが指導の前提となる。
熱意がこもった指導を一心に受け止める能力が必要なのだ。
若気のいたりだが、22歳ごろの俺っちは、
指導を「説教」のことだと思っていた。
老害から説教を受けて目頭が熱くなっていた時期と重なる。
大学を卒業するときは「学生を説教できるようがんばります!」と己を鼓舞していた。
コンビニで弁当を買う際に箸が入っていないときは、
「おい、箸が入ってねえぞ! やる気あんのか」と、
顔を赤くしながら学生のアルバイトに説教していたのである。
今にして思えば、とても、恥ずかしい。
「注意されているうちが花だよ。見限られると無視されるから^ー^」
などと、学校の教師や職場のやつがいっていたが、
これは指導でも何でもない。
指導ってのはこんなもんじゃない。
指導とは、他人をコントロールすることではないからだ。
守破離という言葉がある。
先生とは先に生きると書く。
愛情のこもった指導を心から受けとめ、感動しよう! 感涙しよう。
指導とは全てを教え、全てを教わらなければならない。
そして、自分自身も後世に指導していかなければならないのだ。
教えるのが上手で、教わるのが上手であるのが指導の必定なのだから。