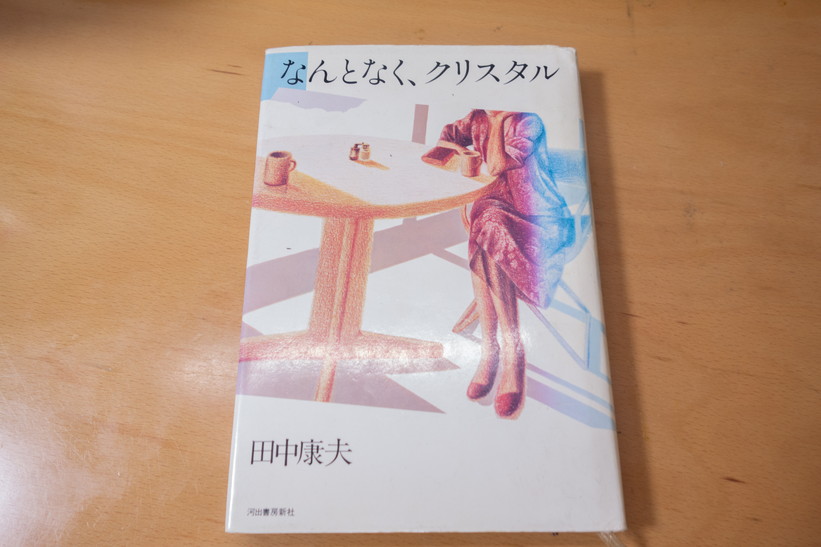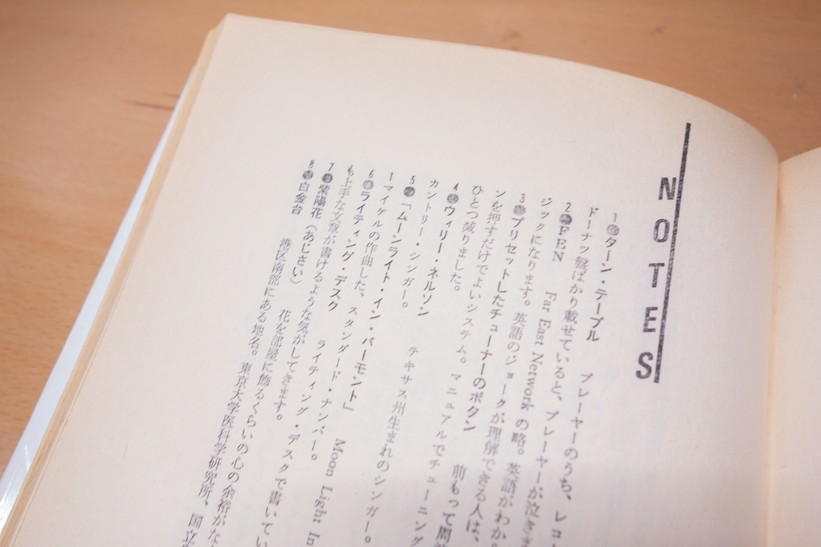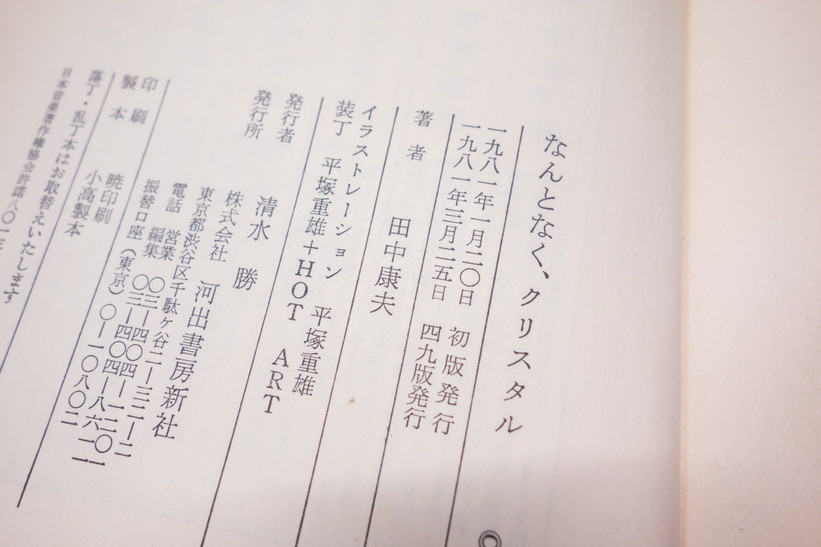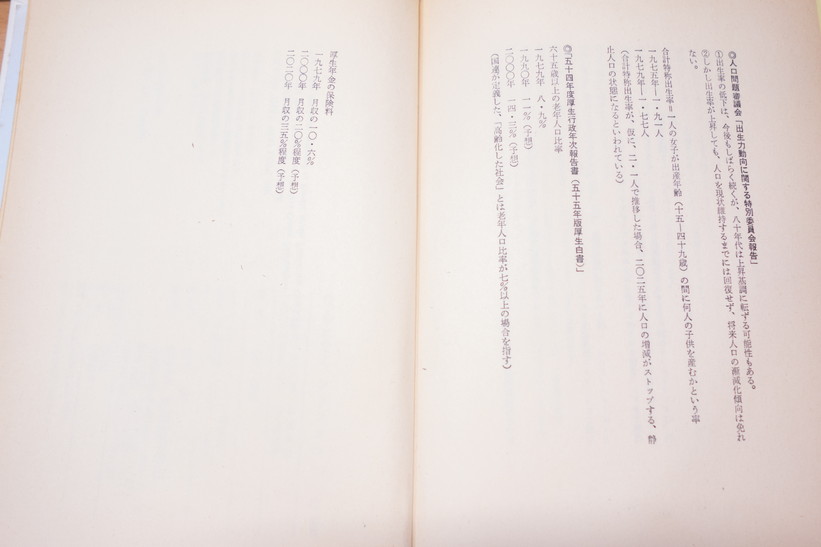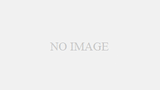???「クリスタルなのよ、きっと生活が。なにも悩みなんて、ありゃしないし……」
???「いつも、二人のまわりには、クリスタルなアトモスフィアが漂っていた」
???「もともと私は多消費型の人だったから、そんなに余裕があるという方でもなかった。だからモデルの仕事は私にとって、結構魅力だった」
著者の田中 康夫は長野県の知事をやっていました。
「鉄製のガードレールを木に変える」なんて言っていたらしいです。
鉄より木のほうがコストがかかりますから、
長野県民からは批判されていたらしいですね^ー^
そんな田中康夫が書いた『なんとなく、クリスタル』ですが、
当時は、斬新かつ清新だったのでしょう。
ポストモダンですし、
最近の言葉でいうなら、City Pop なわけです。
なんクリの特徴は、小説でありながらも、
作者の視点による注釈が多いことでしょうか。
いわば、神の視点です。
当時の流行りや文化、思想、固有名詞などが散見されます。
80年代の風俗や世相を知る、資料としても使えるでしょう。
ハードカバーの巻末に注釈あるので、
いちいち見返さないといけませんね^ー^
調べによると、文庫のほうでは違うらしいです。
1981年に出版された本ですが、
1年で49回も刷られています。
当時のベストセラーだったんでしょう。
水色と白色のしおりヒモがついています。
『なんとなく、クリスタル』のあらすじ
主人公・由利は青山学院大学(青学)に通う、
読書家な帰国子女の女学生でありながらも、
モデルの仕事をしています。
彼女の月収は40万ほどあります。
また、1留の彼ピ・淳一がいます。
その彼氏もスタジオミュージシャンとしてブイブイいわせているのです。
由利は、カネもあり時間もあります。
彼女は遊びかたが上手です。
たとえば……、
「千駄木まで一枚の千代紙を買いに行く。その気力を大切にしたかった。クレージョの夏物セーターを、クレージュのマークのついた紙袋に入れてもらう。そのスノッバリーを大切にしたかった。甘いケーキにならエスプレッソもいいけど、たまにはフランス流に白ワインで食べてみる。そのきどりを大切にしたかった。普段はハマトラやスポーティでも、パーティにはグレースなワンンピースを着て出てみる。その遊びを大切にしたかった。高輪に行ったら東禅寺を訪れてみる。南麻布へ行ったら光林寺を訪れてみる。その余裕を大切にしたかった。こうしたバランス感覚をもったうえで、私は生活を楽しんでみたかった。同じものを買うなら、気分がいい方を選んでみたかった」
「無意識のうちに、なんとなく気分のいい方を選んでみると、今の私の生活になっていた」
「モデルのしごとは、アイデンティティーを考える必要がないからだった。“なんとなく気分の良い生活”をするために、自由になるお金を得ようとう思ってモデルになった直美や私とは、もとから違う気がしてくる」
俺っちの持論に「向いていることは、たいして努力しなくてもできるようになる」というものがあります。
由利も、とくに何も考えず、なんとなく生きているだけで最善の選択をし、
なんとなく良い生活ができているわけです。
つまり、彼女は絶対的にセンス(感性)が良いわけです。
それらは「クリスタル」と形容され、
そんな彼女の「クリスタルな生きかた」が、きらめいていますね。
ブランドなど「あくまで記号にすぎない」という考えかたは、
1980年代としては、かなり前衛的だったのでは?
「ブランドにこだわるなんてことは、バニティーなのかな、と考えてしまう。でも、それで気分がよくなるならいいじゃないか、とも思えてくる」
学生というと、苦学生のイメージですよね。
とにかくカネがないですよね。
令和のいまは、もうそんな学生はいないのかもしれませんけど……。
淳一と由利にはそれがない。
カネを持ちながらも、
学生ですから「時間」もあるんです。
つまり、本当の意味で自由なんです。
最高の青春なんですね。
インターネットとかウインドウズがない、
セカイが電子制御されていないバブルな時代ですけど、
当時としては最高級といえる、
裕福かつ華やかな生活なんでしょう。
そして、由利はそうした記号にも囚われないんです。
また、由利は束縛しません。
すごく、フレキシブルです。
まるで、今の若者みたいな柔軟な思考を持っているのです。
「淳一と私には、おたがいに仕事があった。経済的に、自立している状態だった。だから、私たちは、一人前の社会人であるともいえた。とはいっても、同時に、学生という、社会に出る前の身分も持ち合わせていた。モデルの仕事は、楽しいものだった。学校では知り合えない、多くの友達が、そこにはいた。そして、学校へ行けば、行ったで、多くの愉快な連中がいた。でも、それだけ多くの友だちがいても、一人になると、急にアイデンティーを、一体、どこへ置いたらいいか、わからなくなることがあった。そうした時に、そばにいて離れていかないものが欲しかった。心を許し合えるものが欲しかった。私たちにとっては、それがおたがいに対して望んでいることだった。私のアイデンティティーは、それをモデル・クラブに求めることも、求めようと思えば、できないことではなかった。淳一にしても、グループやスタジオ、大学に求めることができた。でも、私たちにはお互いの存在の方が、より大きなアイデンティティーとすることができた」
「おたがいを、必要以上に束縛し合わずに一緒にいられるのも、考えてみれば、経済的な生活力をおたがいに備えているからなのだった。淳一によってしか与えられない歓びを知った今でも、彼のコントロール下に、“従属”ではなく、“所属”していられるのも、ただ唯一、私がモデルをやっていたからかもしれなかった」
親友や友情、友だちなんかもそうですよね。
メディアがつくりあげた幻想なのに、
互いに友だちだと確認しあうことで「友だち」だと思い込んでいます。
まるで、中世の人々が騎士物語に憧れたように。
そうしたものが連綿と続いているのは不気味ですよね。
「結局、おままごと遊びなのね、私たちの世代の恋愛って。おたがいに、好きです、好きですって言いあって、おままごとをしているのよ」
なんクリの物語の終わりでは、こう綴られています。
「淳一と私は、なにも悩みなんてなく暮らしている。なんとなく気分のよいものを、買ったり、着たり、食べたりする。そして、なんとなく気分のよい音楽を聴いて、なんとなく気分のよりところへ散歩をしに行ったり、遊びに行ったりする。二人が一緒になると、なんとなく気分のいい、クリスタルな生き方ができそうだった。だから、これから十年たった時にも、私は淳一と一緒でありたかった。その時、淳一は、どんなミュージシャンになっているだろうか。単なるキーボード奏者としてだけでなく、アレンジャーとしても、プロデューサーとしても、一流の仕事ができる人になっていてほしい」
「私は、まだモデルを続けているだろうか。三十代になっても、仕事のできるモデルになっていたい。〈三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい〉私は、明治通りとの交差点を通り過ぎて、上り坂となった表参道を走り続ける」
ラストの由利の台詞は、読者の心に響くのでしょうか。
「私は、まだモデルを続けているだろうか。三十代になっても、仕事のできるモデルになっていたい。〈三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい〉私は、明治通りとの交差点を通り過ぎて、上り坂となった表参道を走り続ける」
まあ、由利のいう時代にはならなかったけどな^ー^
由利がいう「三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい」時代は来ねえよ^ー^
また、脚注の最後にですね、ある資料が載っています。
出生率などが書かれた、少子高齢化の資料ですね。
この作品はバブルの時代に執筆されましたが、
まるで、暗澹とした時代が来ることを予見してるかのようですね^ー^
「三十代になった時、シャネルのスーツが似合う雰囲気をもった女性になりたい」のアンサーというべきでしょうか。
オチまで見事です。
現代からみると、
結末の資料ひいては著者の考える、
未来の日本への警鐘の意味がわかるでしょう。
当時は「クリスタル( crystal )」について解剖されたのでしょう。
読解力があるヒトは見抜けたのでしょうけど、
多くのヒトは核心には触れずに、
表層的なクリスタルのことばかりを考えたのは想像できます。
ちなみに『33年後のなんとなく、クリスタル』という2014年ぐらいに出版された続編があります。
俺っちは、読みませんが^ー^